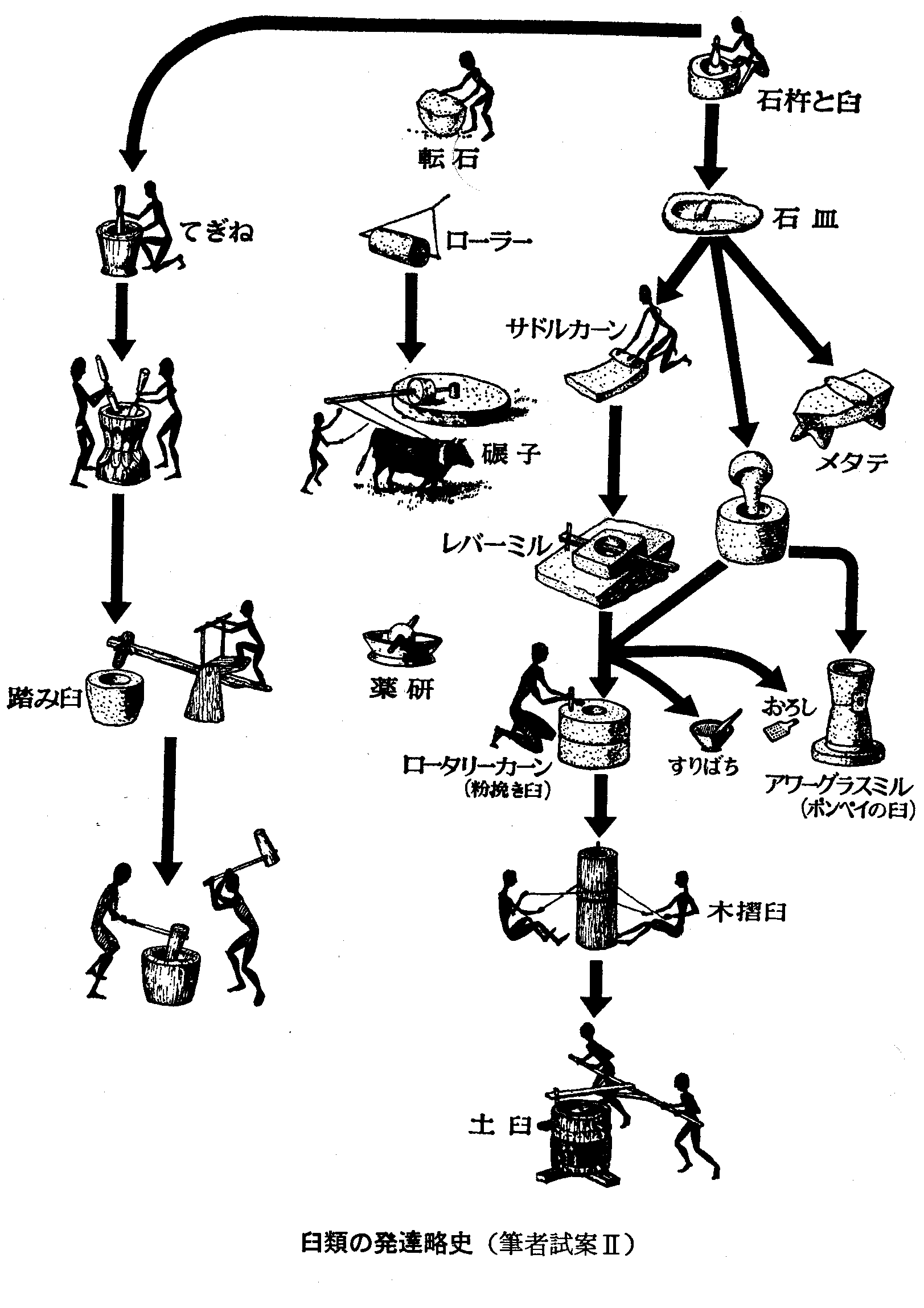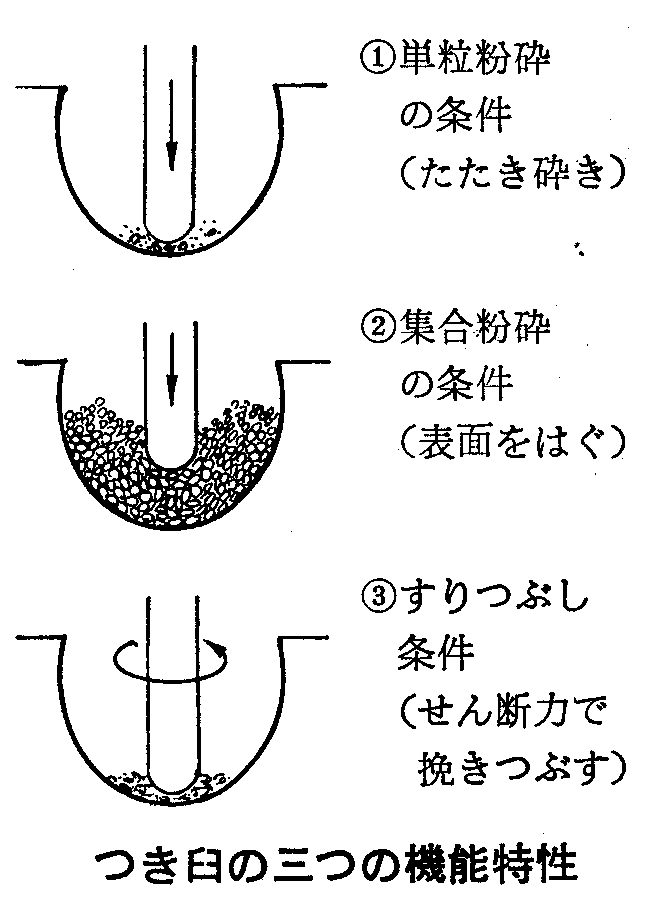 ① 単粒粉砕の条件……臼に少量の穀物などを入れてつくか、多量に入れても、強い力で搗けば杵は粒子層を貫通して、粒を粉に粉砕することができる。製粉はこの条件で行なわれる。
① 単粒粉砕の条件……臼に少量の穀物などを入れてつくか、多量に入れても、強い力で搗けば杵は粒子層を貫通して、粒を粉に粉砕することができる。製粉はこの条件で行なわれる。② 集合粉砕の条件……臼にかなり多量の穀物を入れて搗く場合には、杵は粒子層を貫通せずに粒子層の途中で止まる。このとき杵の衝撃力は粒子層の中に分散し、粒子同士が互いに粒子表面で摩擦し合う。表面をわずかにぬらすことによって、表面摩擦係数が増すとともに表層が歌かくなり、粒子表面にかかる剪断(せんだん)力によって、粒子表面がはがれる。米の脱ぷ、精白はこれである。
③ すりつぶし条件……杵を押しつけながら回転させると、すりつぶしが行なわれる。小麦粒は①の方法でも粉砕できるが、粒に弾性があるので、むしろ、すりつぶした方が粉砕しやすい。挽き臼とすりばちはこの機能特性を発達させたものと考えられる。
臼の原始形態は石の杵と臼であり、これを基本として①〜③の機能特性を分化発達させてゆく過程で、人類は多様な臼類(mills)を生み出した。『臼』(49―53ページ)に筆者試案Iを示したが、それを多少修正したものを、ここに試案IIとして掲げておく。万能の搗き臼と単能の挽き臼やすりばちなど、このように理解すると、臼類の進化論が成り立つのである。」
三輪茂雄『石臼探訪』クオリ、1978年,p27,p.29