- パソコンの出荷台数・稼働台数の膨大さ --- 情報処理のハードウェア的プラットフォームとしての膨大さ、価格の相対的安さ、人々の学習コストの相対的低さ
- パソコンのハードウェア的レベルにおける情報処理能力(CPU、HDD、メモリ、バスetc)の増大 --- サーバーとして要求されるハードウェア的性能のクリア
-
インターネットの普及およびパソコンの性能向上と価格低下により、パソコンは企業や行政機関だけでなく、家庭でも広く使用されるようになった。世界におけるパソコンの推定出荷台数は、1998年に9331万台であったのが、1999年に1億1763万台となり、史上はじめて年間1億台を越える出荷量となった。その後も2000年 1億3428万台、2001年 1億2893万台、2002年 1億5230万台、2003年に1億6886万台と年間1億台を超え、年間2億台に近くなっている。
[関連データ]世界におけるパソコンの年間出荷台数推計値
なおそうした結果として、2002年4月に世界におけるパソコンの累計出荷台数が、1975年のMITS社Altair8800から数えてついに10億台を突破した、と言われている。
日本における2003年度のパソコンの本体総出荷台数(国内出荷+輸出)は1,156万8千台(前年同期比111%)、本体総出荷金額は1兆7,164億円(同101%)であった。
これに対して、メインフレームコンピュータの2003国内出荷金額は2,625億円(前年度比71%)、出荷台数1,241台(同95%)であり、金額ベースではパソコン市場の約1/7に過ぎない。ミッドレンジコンピュータの2003年度の出荷金額は5,313億円(前年度比86%)、出荷台数で186,453台(同101%)で金額ベースではパソコン市場の約1/3に過ぎない。2003年度のワークステーションの出荷金額は494億円(前年度比71%)、出荷台数では67,768台(同97%)である。
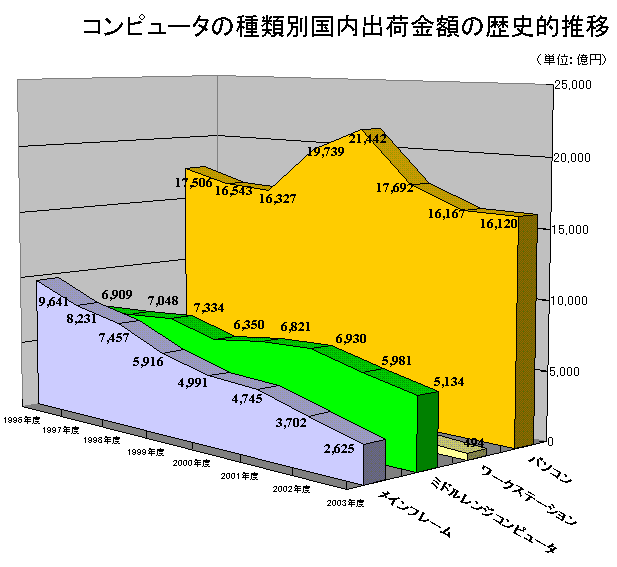
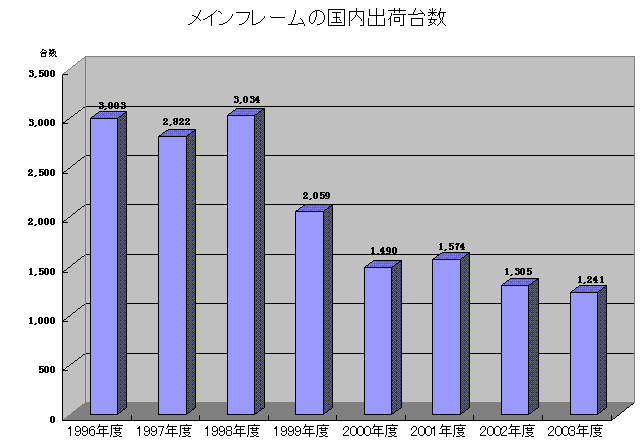
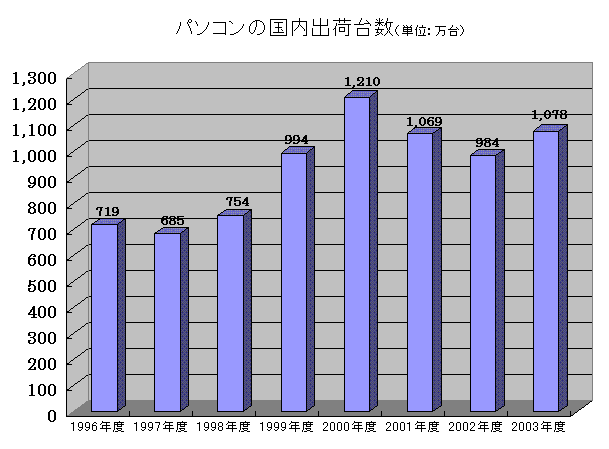
- サーバー用OSとしての安定性・信頼性 --- サーバ用OSをターゲットとして開発されたUNIX系OSとしてのLinuxの安定性・信頼性、多彩なデバイスのサポートやGUIの実装などパソコン用OSをターゲットとして開発されたWindowsNTの相対的な「能力の低さ」
サーバー用OSとしてはLinuxの方がWindows NTよりも安定していることはよく強調されることです。
Windows NTを長時間(1日〜1週間)にわたって連続稼動させると、メモリリークなどを原因としてある日突然にシステムのハングアップが起こることは、下記のWebページの記述などに見られるようによく知られていることで、対策ソフトがいくつも出ています。
http://www.contec.co.jp/comm/info990728.htm
http://premium.nikkeibp.co.jp/linux/special/special05/3.shtml
安定性や信頼性について最も評価されているのは商用UNIXですが、Linuxもそれに次ぐ高い評価を受けています。
『Linux白書2003』資料1-1-72「サーバーOS別今後利用拡大の理由」では「安定しているので」と回答したユーザーの割合は、商用UNIXの76.7%に対して、Linuxが69.9%、Windows2000/NT Serverが40.4%となっています。
『Linux白書2003』資料1-1-73「サーバーOS別今後利用しない/利用縮小の理由(2001-2002)」では「信頼性や安定性に問題がある」という回答理由の割合が、Windows200 Serverが67.6%と極めて高いのに対して、商用UNIXが2.2%、Linuxが11.8%となっています。
『Linux白書2003』
http://home.impress.co.jp/books/linuxwp2003/
-
ただしWidowsXPは、この点に関してWindows NTよりもかなり改善しているように思われる。WidowsXPはWindowsNTと比べてメモリリークの問題はかなり改善されており、システムとしての安定性が高くなっている、と思われる。
なおこうした問題に関するユーザー側の判断は、「無償」OSと「有償」OSとではかなりその判断結果に違いがある可能性があるので、注意する必要がある。(100円ショップの商品に対する消費者の満足度は高いが、それはあくまでも価格との相対的比較に基づくものに過ぎません。100円ショップが200円ショップなり300円ショップになれば、商品に対する消費者の満足度はかなり低下する可能性があります。同じことが「無償」ソフトと「有償」ソフトの場合にも当てはまります。)
オープンソースソフトウェア関連のリンク集
- 日経BP社「Linuxソリューション」
- Japan Linux.Com 「オープンソース」
- オープンソースと政府
- OSDLジャパン『公的機関・自治体システムへの オープンソース適用性に関する報告書』(2003/10/31)
http://premium.nikkeibp.co.jp/linux/index.shtml
http://japan.linux.com/opensource/
http://oss.mri.co.jp/
http://www.osdl.jp/docs/white_paper.pdf
-
ハードウェアやユーティリティ・ソフト、開発言語ソフトなども含めた情報システムの構築・維持に関わるトータル・コストがUNIXの場合よりも低く、Windowsの場合とほぼ同じである。
- Linuxソフトウェアそれ自体の低コスト性
- 開発ソフトやアプリケーション・ソフトなどの関連ソフトウェアに関わる低コスト性
- ハードウェアに関わる低コスト性
-
Linuxカーネルは無償で入手可能
OSとしてLinuxを機能させるのに必要なソフトも無償もしくはWIndowsOSと比べてかなり低価格で入手可能(ディストリビューション)
-
Linuxは、それに関連する開発ソフトなどの周辺ツールや、業務をこなすためのワープロなどのアプリケーションソフトもオープンソースで提供されているものがあり、ソフトに関してもトータル・コストを抑えることができる。
- Linuxはインテル系CPUを搭載したパソコンでも稼働するため、OSを動かすためのコンピュータ本体や必要な周辺機器(増設HDD,プリンター、メモリーなど)などハードウェアに関わるコストがUNIXの場合よりも低い。
Linux OSは「基本的には無料である」ということによるコストメリットとともに、それを動かすためのコンピュータのハードウェアに関わるコストがUNIXに比べてかなり安いため、UNIXの場合と比べてかなり安価なシステムを構築できるというメリットがある。
インテル系CPUを積んだパソコンは大量生産=大量販売されているため、そうしたパソコン用の増設HDD,増設メモリ、プリンターなどのハードウェアに関する大量生産=大量販売によるスケールメリットをLinuxは享受することができます。