(1)授業ガイダンス
A.授業の基本的目標
1)MOT(Management of Technology,技術経営)入門
-
MOTに対する社会的関心の高まりの背景 ---- 企業の競争力を規定する重要な要因の一つとしての技術力、技術管理力(技術マネジメント力)
-
技術プロセスのマネジメントが重要であることは企業競争力の重要な構成要素が技術競争力である製造業においては従来から認識されてきた。しかし絶えざる技術革新が激しく進む現代では、製造業に限らず様々な分野の企業において、「技術革新への素早い対応」「変化する技術システムに対する合理的管理能力の差異が企業競争力を左右するようになってきている。
ユビキタス社会といった用語に示されているように、特にIT分野におけるすさまじい技術革新とその社会的利用の急速な進展は、情報通信技術分野における技術発展の将来的発展を見越した合理的対応や、情報処理システムや情報通信システムに対する合理的管理能力の育成が重要になってきている。
こうした状況の中で、「経営感覚を持った技術者」および「技術感覚を持った経営者」の育成が社会的に強く求められるようになってきている。
-
技術プロセスをマネジメントするには、「技術プロセスそのものを直接的にマネジメントしようとするやり方」と、「技術プロセスに関わっている技術者をマネジメントすることで技術プロセスを間接的にマネジメントしようとするやり方」の2種類がある。
2)Innovation(技術革新)の歴史的構造の解明 --- needsとseedsの相互連関
-
技術開発の方向性の決定や、利用(採用)する技術の選択にあたっては、「技術発展とはなにか?」、「技術発展はどのような形で生じるのか?」、「技術革新はどのような形で進行するものなのか?」といったことの把握が重要である。
B.授業の基本的視点と基本的構成
1)「学び問うこと」としての学問
a.「何が常識的見解なのか?」を踏まえた上で、その常識的見解の根拠が何かを考察すること
b.「常識的見解は本当に正しいのか?」を様々な視点から批判的に検討すること
c.理論に基づく考察とデータに基づく考察という二つの視点から相互的かつ総合的に検討すること
一つの問題に対する<理論的視点からの検討>と、<様々な事実との一致・不一致を調べるというデータ的視点からの検討>
理論とデータの相互的検討・・・<理論が正しいかどうかに関するデータに基づく検討>と<データにどのような意味があるのかやデータは本当に正しいのかということに関する理論的検討>
理論とデータの相互的検討・・・<理論が正しいかどうかに関するデータに基づく検討>と<データにどのような意味があるのかやデータは本当に正しいのかということに関する理論的検討>
データ的視点には<現在的視点からの検証>(現在的事実に基づく検証)と<歴史的視点からの検証>(歴史的事実に基づく検証)の二つがある
力学的運動とのアナロジー的発想で現実を分析すること(現在位置x、速度v=dx/dt、加速度a=d2x/dt2という三つのレベルで過去・現在・未来を捉えること)が重要
すなわち、
力学的運動とのアナロジー的発想で現実を分析すること(現在位置x、速度v=dx/dt、加速度a=d2x/dt2という三つのレベルで過去・現在・未来を捉えること)が重要
すなわち、
-
a>「現在どうなっているのか?現在はどのような歴史的段階にあるのか?」といった現在の位置に関わる分析
b>「現在はどのようなスピードでどのような方向に向かっているのか?現在は次にどのような歴史的段階にどのようなスピードで向かっているのか?」などといった現在の将来的発展方向とその方向に向かう進展スピードに関わる分析
c>「将来的発展方向(あるいは将来的進展方向)を規定している要因にはどのようなものがあるのか?将来的発展方向に向かうスピードを規定している要因にはどのようなものがあるのか?将来的発展方向を変化させる可能性のある要因にはどのようなものがあるのか?」などといった将来的発展方向およびその進展スピードを規定している要因に関わる分析
2)講義で前提しているモノの見方・考え方
「なぜ、授業で歴史的事実というデータをこまかく教えるのか?」「なぜ、授業でコンピュータの構造に関する事実というデータをこまかく教えるのか?」という疑問を持つ人もいるかと思いますが、学問的考察は下記のように「データから出発して、データに帰る」ということを何度も繰り返すことが基本です。
すなわち、「データに基づいて理論的仮説を立てる」ことからはじめて、次に「その理論的仮説がどの程度まで正しいのか、あるいはまったく誤っているのかをデータに基づいて判断する(」ということを無限に繰り返すことで正しい科学的理論を形成することができます。(「データから理論」へと向かう抽象化[帰納]と、「理論からデータ」へと向かう具象化[演繹]という二つのプロセスの無限循環が学問的営みです。)
後期の「技術戦略論」の授業では、「企業がどのような技術戦略をとっているのか?」ということに関してデータに基づいて解明する(データから技術戦略という構造を仮説的に導き出す)とともに、「どのような戦略がどのような状況の下で有効なのか、あるいは無効なのか」ということに関する理論的仮説をデータに基づいて検証する、ということを行う予定です。
すなわち、「データに基づいて理論的仮説を立てる」ことからはじめて、次に「その理論的仮説がどの程度まで正しいのか、あるいはまったく誤っているのかをデータに基づいて判断する(」ということを無限に繰り返すことで正しい科学的理論を形成することができます。(「データから理論」へと向かう抽象化[帰納]と、「理論からデータ」へと向かう具象化[演繹]という二つのプロセスの無限循環が学問的営みです。)
後期の「技術戦略論」の授業では、「企業がどのような技術戦略をとっているのか?」ということに関してデータに基づいて解明する(データから技術戦略という構造を仮説的に導き出す)とともに、「どのような戦略がどのような状況の下で有効なのか、あるいは無効なのか」ということに関する理論的仮説をデータに基づいて検証する、ということを行う予定です。
a.<データ>から<構造>へ ・・・ データ←→一次的連関←→構造
b.<構造>から<理論>へ
c.<理論>による<データ>や<構造>の説明・予測
-
(1)諸データの形成(歴史+現状に関する生データ)
↓
(2)諸データ間の1次的連関の生成(生データの分類など、生データ間の類似度や親近度などによる区分)
↓
(3)1次的連関の中の存在的諸構造の発見(1次的構造=データとしての構造)
上記で注意すべきポイント
実際には上記のような単線的流れではなく、下記のように循環的構造が存在する。
-
(1)と(2)の間の循環的作業[(1)→(2)→(1)→(2)→(1)・・・]によるデータおよび1次的連関の相互的生成
(2)と(3)の間の循環的作業[(2)→(3)→(2)→(3)→(2)・・・]による1次的連関および構造の相互的生成
b.<構造>から<理論>へ
-
(1)存在的諸構造の間の連関や構造(2次的連関、2次的構造)=データとしての連関・構造
↓
(2)連関や構造から理論の「発見法」的導出
c.<理論>による<データ>や<構造>の説明・予測
-
理論に基づく連関や構造の説明・予測
3>技術という視点から企業経営を考える授業としての「経営技術論」
多様な技術的選択肢、および、市場の将来的変化や技術の将来的発展による潜在的な技術的選択肢を対象として、現在および将来の「市場」環境・「技術」環境などとの連関、および、「時間」的制約・「コスト」的制約・「リソース」制約(投入可能な経営資源や利用可能な技術開発能力)の諸要因を考慮に入れながら、どのような戦略的な技術選択を行うべきなのか、どのようなやり方でどのような方向に向けた技術開発を戦略的に行うべきなのかを過去の事例研究に基づきながら論じる。
4>「技術」という用語の持つ多様性、および、「技術」を論じるための視点の多様性
a.ニーズ(needs) vs シーズ(seeds)
→技術の相互連関(技術発展のネットワーク構造)
「発明の母」であるニーズ(必要)と「発明の父」であるシーズ(技術的な種・先行する技術開発)
ニーズにも、社会的ニーズ(ある製品やサービスに対するマーケット・ニーズ)と技術的ニーズ(ある製品やサービスの開発に必要な要素的技術に対するニーズ)の二種類を区別する必要がある
b.多様な技術的方式の相互競争と棲み分け
c.Product Innovation vs Process Innovation
i>Product Innovation
製品そのものに関わる技術(製品の基本的な技術的性能や独自性に関わる技術)についてのイノベーション
ii>Process Innovation
製品の製造に関わる技術(製品の製造に関わる技術、製品コストや品質・信頼性に関わる技術)に関するイノベーション
Product Innovation と Process Innovationの関連と差異に注意が必要
-
productに関して、組立型製品(ex.マイクロプロセッサー+マザーボード+メモリ+HDD+DVD+PCケース→パソコン)、加工型製品(工作機械などによる加工によって生産される製品)、素材型製品(鉄、ガラスなど)ごとにProduct Innovation/ Process Innovationのあり方は異なる
d.要素的技術 vs 要素的技術の統合(技術統合)
(2)「Needs-Seeds視点から見たイノベーションの構造」
- 日本開発工学会主催 第2回オープンイノベーション連続シンポジウム開催のご案内における梶本修身(株式会社総合医科学研究所 創業者 非常勤取締役、大阪市立大学医学部客員助教授)氏の発言
- 植之原道行(多摩大学名誉教授・元NEC研究開発本部長)の発言
- 宮原秀夫(大阪大学総長)氏に対するインタビュー記録
- Kazumasa Niimi(2002),"An Economic Analysis of "Market-Needs Oriented Childcare Reform"",Japan Research Quarterly, Autumn 2002
http://www.jri.co.jp/JRQ/overview/2002/200204/JRQ200204childcare.html
- 藤田 昌一「「内部技術」と「外部技術」」(『トンネルと地下』2001年11月号 巻頭言)
- ボーズ株式会社のWebページの一節 http://www.bose.co.jp/technologies/(2005.05.15アクセス)
- 東京大学理学部化学科「学科の概要」のカリキュラム紹介の中で教育理念を述べた文章の一節(同Webページの文末部分) (2005.05.15アクセス)
- フリービット株式会社「IPv6に化関わる木村太郎氏へのインタビューに関するMedia LifeStyle 取材メモ」 (2005.05.15アクセス)
- インテルの最初の16ビットマイクロプロセッサーに対応した16ビットOSであるQ-DOS
- ブランド力
- 現在の価格
- 現在の性能
- 現在の価格対性能比
- 将来的可能性に対する予想・期待度
- 「nikkeibp.jp 技術と経営の総合情報」
http://nikkeibp.jp/
A.よく見られる三つの見解 --- needs主導説,seeds主導説,needs-seeds相導(協働)説
1>needs主導説>新たな技術革新は必要(needs)から生み出される(Needs-Oriented Innovation)→Market-In的発想,Market-driven的発想
「社会の需要、市場の需要、消費者の需要から出発するNeeds-orientedな技術革新でなければビジネスとしては成立しない」というような考え方
ネット上の事例
http://kaihatsu.hp.infoseek.co.jp/sympo050427.pdf
-
「さらに、「Needs-oriented R&D」が上げられる。これは、需要からの出発ということである。 大学発の場合は、シーズ発想的なものが多いが、社会のニーズを満たせなければビジネスは成立しない。」
「産業競争力強化の観点から技術経営(MOT)の必要性を考える」というテーマでのIEEE Engineering Management Society Japan Chapter会合における発言
http://www.glocom.ac.jp/users/shoji/MS/IEEE-MOT.html
-
「大学では、次のようなことを教えてほしい。社会が変わり技術者には難しい時代に入っている。モード1のサイエンスは、現実の社会の中から基礎的課題を抽出して社会のニーズに応えるモード2に変わらなくてはいけない。大学の研究もneeds orientedという認識を持ってほしい。技術経営の意識改革なくしては世界競争に勝てないのだ。」
http://www.zkai.co.jp/z-style/special/003_top2.asp
-
宮原秀夫氏は上述のインタビューの中で、「商品開発する際に、専門の人はその専門分野の立場ばかりで物を作ろうとする。誰が欲しがっているのかより、あるいはお客さまの要望などよりも、自分の思いこみを優先させて、その延長で商品開発してしまう。その結果、せっかく開発してもその商品は使えない」というインタビューアの質問に答えて、「そうなんです。要するに今までほとんどですね、シーズオリエンテッド(seeds-oriented:製品開発などで、技術などの種(seed)がまず存在し、それを新たな製品や技術にしようとすること)、つまりこういう技術があるからこういうものを作っていたと。そうしますとね、結果的に技術者エゴの製品ができてくるわけです。それはユーザーにとっては使いにくいものだったりするわけですよ。・・・(途中省略)・・・ユーザーのニーズオリエンテッド(needs-oriented:製品開発などで、要求をもとに、開発を促進していくこと)からどういうものが欲しいのか、そのためにどういう技術を開発しなければいけないかということが大事です。おっしゃる通り、ニーズオリエンテッドの方向へ見直されているんです。」と答えている。
関連参考文献
http://www.tt.rim.or.jp/~s-fujita/037zuihitsuNAIBUGIJUTU.htm
-
ニーズ・オリエンテッドの技術を「内部技術」と「外部技術」の2種類に分けて論じている。前者の「内部技術」が授業における技術的ニーズに対応した技術開発にあたり、後者の「外部技術」が授業におけるマーケットニーズに対応した技術開発にあたると思われる。
2>seeds主導説>新たな技術革新はシーズ(seeds)から生み出される(Seeds-Oriented Innovation)→Product-Out的発想,Technology-driven的発想
<発想1・・・ラジカルな技術革新はSeeds-Oriented Innovationである>
-
「本来的な意味での技術革新、真にラジカルな技術革新は、マーケット・ニーズに対応した技術開発によってではなく、seeds-orientedな技術革新である」
<発想2・・・技術的シーズがマーケット・ニーズに先行する>
-
「発明は必要からではなく好奇心から生み出される」(実用新案やアイデアは必要から生み出されるのだが、発明はそれらとは異なる)
「発明などの技術的シーズがマーケット・ニーズに先行する」(TV放送を見たいというマーケット・ニーズがあってTVが開発されたわけではない)
「技術的シーズが先行し、それを商品として活かすのはその後になる」
「まず最初は製品をきちんと完成させることが最初だ。製品を作り出した後で実際に売り込み・販売が可能になる」>
「次々から次へと技術革新が進行している現代、かつ、企業間における技術革新競争が激しい現代において、他企業に対する技術的優位性を確保・持続・挽回したり技術的差別化を実現するためには、現時点におけるマーケット・ニーズだけを見据えた技術開発ではダメだ。他企業も含めた将来的技術革新の予測、および、そうした将来的技術革新に基づく市場環境・技術環境の変化の予測に基づき、まだ不確定で本当にマーケット・ニーズがあるかどうか分からないものであっても、技術革新を進める必要がある。」
ネット上の事例
「必要は発明の母ではない・・・電球が発明されたのは、世界で明かりを求める声が上がったからではありません。18世紀半ばの人々にとって、暗がりを通り抜ける時の明かりはガス灯やろうそくで十分だったのです。電球の発明は必要に駆られてではなく、単なる好奇心から始められました。事実、発明や革新および革命的と思われる新しいアイデアは全て、同じような好奇心から生まれてきたのです。」
http://www.chem.s.u-tokyo.ac.jp/kyomu/gakubu/Shingaku-Annai/gaiyou.html
21世紀を控え,我が国の科学技術の発展に基礎的研究推進が強く求められている。本化学科は「基礎」すなわちneeds-orientedよりseeds-orientedをより尊ぶことを旨とする。良き基礎研究の結果は,やがて良き応用を生み出すという考えである。
http://start.feel6.jp/lifestyle/kimura.html
「(ジャーナリストの木村太郎氏によると)メディアの世界にとっては「必要が発明の母ではなく、発明が必要の母」とのことである。テレビのカラー化、衛星放送の開始、などなど様々な「発明」の後に、現場が「必要」を見つけていくエピソードの数々を聞かせていただいたが、大変面白い。一例を紹介すると、NHK時代に「○月○日付けで、全てのニュース番組はカラー化を生かした取材をすること」という通達が入る。そこで現場は、何をしていいのか分からずに「花ばっかり撮っていた」とのことである。
このようにメディアの変遷を俯瞰されて来た立場から、IPv6化も似たような背景であるという意見を持たれている。通信事業者や家電機器メーカーにとっての必要はあるが、一般消費者にとっての必要はそれほど見えていない。ただ、必要を感じる人たちが、必死で頭を絞ることで、IPv6も必ず将来は「当然必要な存在」となり、普及のために頭を絞っていたという事実さえが、エピソードになるとおっしゃっていた。普及の為に尽力している我々にとっては心強い一言であった。」
このようにメディアの変遷を俯瞰されて来た立場から、IPv6化も似たような背景であるという意見を持たれている。通信事業者や家電機器メーカーにとっての必要はあるが、一般消費者にとっての必要はそれほど見えていない。ただ、必要を感じる人たちが、必死で頭を絞ることで、IPv6も必ず将来は「当然必要な存在」となり、普及のために頭を絞っていたという事実さえが、エピソードになるとおっしゃっていた。普及の為に尽力している我々にとっては心強い一言であった。」
考察すべき事例
マイクロソフト社が世界最初の商用16ビットパソコンであるIBM PCに対する16ビットOSのMS-DOSのプロトタイプとして買収したQDOS(Quick and Dirty Operating System)は、そうした16ビットOSを必要とする16ビットパソコンという製品の開発よりも前にすでに製作されていた。
現在のパソコンのドミナント・デザインとも言えるIBM PCという製品は、1980年夏頃から開発が開始され1981年に販売開始となったが、QDOSはIBM PCの開発とはまったく独立にTim Patersonによって1980年に完成されていた。
16ビットマイクロプロセッサーに対応した16ビットOSの開発というイノベーション事例は、「マーケット・ニーズに対応したイノベーション」という一般的イメージとはあまり適合的ではない。
現在のパソコンのドミナント・デザインとも言えるIBM PCという製品は、1980年夏頃から開発が開始され1981年に販売開始となったが、QDOSはIBM PCの開発とはまったく独立にTim Patersonによって1980年に完成されていた。
16ビットマイクロプロセッサーに対応した16ビットOSの開発というイノベーション事例は、「マーケット・ニーズに対応したイノベーション」という一般的イメージとはあまり適合的ではない。
3.needsとseedsの協働説>「必要(needs)が発明の母であるとすれば、シーズ(seeds)は発明の父である。技術革新の生起構造の理解には必要(needs)とシーズ(seeds)の両要素を考慮する必要がある。」
B.ニーズの階層性(客観的必要性およびそれに対する認識としての欲求に関する階層的存在構造)と多様性・・・needs-wantsスペクトル
-
個人を人間として考察した場合に、人間に関して良く知られている類型的考察 --- homo sapiens,homo faber,homo ludens ---に示されているように、その欲求の大きさに個人的差異があるにしても、「知」「モノの製作(労働)」「娯楽」への欲求は人間に固有な欲求と考えられている。
こうした抽象的欲求という次元におけるニーズは、実際の場面ではある特定の時刻にある特定の形態に具体化されて初めて欲求が満たされることになるのであるが、その具体化は下表のような階層的構造を持っている。ある一つの抽象的欲求の具体的充足は多種多様な形で展開されることになる。
それゆえ「ニーズを満たす」ということは決して単純な事柄ではない。「ニーズを満たす技術的発明が社会的に成功し、ニーズを満たさない技術的発明は社会的に失敗する」という見解は単純すぎる。ニーズへの対応・非対応が技術的発明の成功と失敗とを分ける絶対的分水嶺ではない。
needs-wantsスペクトル表(1)
| ←より抽象的 | より具体的→ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.TV | |||||
| a.地上波アナログ放送のTVを見る | |||||
| b.地上波デジタル放送のTVを見る | |||||
| c.衛星波アナログ放送のTVを見る | |||||
| d.衛星波デジタル放送のTVを見る | |||||
| e.CATVを見る | |||||
| f.インターネットでTVを見る | |||||
| 2.映画 | |||||
| a.映画館で映画を見る | |||||
| b.DVDで映画を見る | |||||
| c.TV放送で映画を見る | |||||
| 3.旅行 | |||||
| a.国内旅行 | |||||
| b.海外旅行 | |||||
| 4.スポーツ | |||||
| a.野球 | |||||
| (i)プロ野球 | |||||
| アメリカのプロ野球の試合観戦 | |||||
| 日本のプロ野球の試合観戦 | |||||
| | | セリーグの試合の観戦 | ||||
| | | 阪神−巨人戦の観戦 | ||||
| | | 中日−巨人戦の観戦 | ||||
| | | ヤクルト−広島戦の観戦 | ||||
| | | ヤクルト−横浜戦の観戦 | ||||
| | | パリーグの試合の観戦 | ||||
| | | セパ両リーグの交流試合の観戦 | ||||
| (ii)アマチュア野球 | |||||
| 6大学野球試合の観戦 | |||||
| 実際にプレーする | |||||
| b.ゴルフ | |||||
| c.サッカー | |||||
| d.バレーボール | |||||
| e.スキー | |||||
| 5.遊園地 | |||||
| 6.ゲーム機 | |||||
| SonyのPlayStationで遊ぶ | |||||
| MicrosoftのXboxで遊ぶ | |||||
| 任天堂のニンテンドーDSで遊ぶ | |||||
C.ニーズの存在構造の歴史的変化、および、そうした変化を引き起こす一つの要因としての技術革新
- needs主導説,seeds主導説,needs-seeds相導説のどれが正しいのか、あるいは、それぞれの説の妥当領域はどのようなものであるかを考える際には、上記のようなニーズの階層性や多様性を、過去−現在−将来という歴史的変化の相の中できちんと考えた上で議論する必要がある。
というのも、上記のneeds-wantsスペクトル表(1)は、現時点ではそれなりに正しいモノであるが、過去にはこれとは異なるものであった。19世紀には、日本のプロ野球もSonyのPlayStationも存在しなかったのである。技術革新や社会のあり方の変化とともに、needs-wantsスペクトル表(1)の具体的存在構造も変化するのである。
そのため「ニーズに応える」といっても、「応える」べきニーズは具体的レベルにおいては決して固定的=普遍的なものではない。さまざまな要因によって変化するのである。
コトラーは、needsとwantsを区別した上で、「顧客がある特定のwantsそれ自体を求める」というようにではなく、「顧客はある特定のneedsを満たすためにある特定のwantsを選択しているに過ぎない」というように捉えるべきであるとしている。ある特定のneedsを満たすwantsは一般には複数個存在するということや、現代では当該needsを満たし人々のwantsの対象となりうる可能性を持った製品が技術発展にともなって日々新たに開発=販売されていることなどをあわせて考えれば、wantsの具体的存在構造も日々変化していることになる。
新たな技術発展によって生み出された技術的発明は、最初はさほどのマーケット・ニーズがなくても、その技術的発明の引き続く改良(そしてシステム製品の場合には関連する技術的発明の整備)、および、その技術的発明の意味に関する社会的理解の進展などにつれて社会的に普及することになる。
実際、1800年のボルタの電池の発明以後、電気関連の科学的知識や技術的知識の拡大につれ、様々な技術的発明がなされた。そして最終的にエジソンによる蓄音機の発明、ベルによる電話の発明、大規模発電所−送電網−配電網といった電力ネットの形成など19世紀における電気技術の進展はそれまで存在しなかったマーケット・ニーズを多数生み出した。
同じようなことは現代においても様々な分野で起こっている。TV、任天堂の「ファミコン」、ビクターの「VHS方式VTR」など技術発展によって新たに創り出された製品は、TV放送による広告宣伝市場・ゲーム機市場・ゲームソフト市場・レンタルビデオ市場などそれまでまったく存在していなかった市場を新たに生み出した。
そうした新しいマーケット・ニーズの登場の結果として、それまで支配的であったニーズが相対的に地位を低めるか、消失していく。(TV放送の本格的普及の後にはラジオ放送がその地位を大幅に低下させてしまったし、ゲーム機の普及はオモチャに対するニーズをかなり減少させた。)
-
TV放送に関わる多数の技術革新とそれにともなうニーズのあり方の変化
-
白黒TVの技術開発 → TV放送局の新設による白黒TV放送の開始 → カラーTVの技術開発 → 既存TV放送局によるカラーTV放送の開始 → 衛生TV放送技術の開発 → 衛生TV放送局の誕生 → インターネット放送技術の開発 → インターネット放送局の新規誕生!?
| 1.地上波TV | |||
| a.地上波アナログ放送 | |||
| (i)VHF放送 | |||
| (ii)UHF放送 | |||
| b.地上波デジタル放送 | |||
| 2.衛星波TV | |||
| a.アナログ衛星放送 | |||
| b.デジタル衛星放送 | |||
| 3.CATV | |||
| 4.インターネットTV |
D.ニーズの新しい具体化としての技術革新
-
上記の「needs-wantsスペクトル表(1)」に示されているようなニーズの階層性および多様性という視点から技術的発展プロセスを捉えてみると、何らのニーズにも対応していないような技術的発明はない。ある特定の技術的発明(あるいは技術的発展)は、「ある階層のある特定のニーズを満たしている」が、「同じ階層の別のニーズを満たさない」「別な階層のニーズを満たさない」というだけのことなのである。
一般に言われている「ニーズに対応していない技術的発明」とは、他の技術的発明よりもニーズへの対応がかなり低いか、対応しているニーズの社会的必要度が他のニーズよりもかなり小さいということに過ぎないことが多い。しかしこうした量的大小の問題は、実際に製品として完成した直後には(そして時にはしばらく時間が経過した後でも)判然とはしないことが多い。
そうであるから、技術開発の開始前に「ニーズとの対応」の大小を正確に知ることはかなり難しい。開発前に市場調査をおこなっても、実際にははずれることも多い。優秀なセールスマンが顧客の意見を聞いた結果が否定的なものであっても、それは新しい技術開発や製品開発の社会的普及の失敗を意味するとは限らない。IBMがコンピュータ事業に乗り出そうとして、事前に顧客の意見を聞いた時にも否定的見解の方が多かったと言われている。
-
<注>IBMが出遅れていたパソコン事業にIBM PCで乗り出した時も、その予想販売台数は実際よりもかなり少ないものでしかなかった。クリステンセンは『イノベーションのジレンマ』の中でこうした事例をいくつも挙げている。
手書き文字をタイプ文字に置き換えることを可能にした英文タイプライター、文章作成という作業を文字を書くからキーボードを打つことに変えたワープロ専用機、テレビをリアルタイムで見る必要をなくすことや家庭で映画を見ることを可能にしたVTR、歩きながら音楽を聴くことを可能にしたウォークマン、大量の文書のデジタル保存やデータベース処理や家庭でのビデオ編集などを個人に可能にさせたパーソナル・コンピュータなどそれまでに存在しなかった分野の製品の開発は、新しいライフスタイルや新しい作業のやり方の提案などニーズの「新しい具体化」(すなわち、それまでそんざいしなかった新しいwantsの形成)を含んでいる。こうした場合には、ニーズの具体化というプロセスそれ自体が新しい技術開発や製品開発そのものとなっている。すなわち、ニーズの新しい具体化のプロセス(新しいwantsの創造プロセス)そのものが技術革新プロセスとなっているのである。
E.ニーズの性格分類・・・・マーケット・ニーズ vs 技術的ニーズ
ニーズといっても、具体的場面においてはそれがどのような存在性格を持つモノであるかをきちんと分けて考察する必要がある。特に、マーケット・ニーズ(ある製品やサービスに対するマーケット・ニーズ;社会的ニーズ、消費者集団が持つ消費的ニーズ)と技術的ニーズ(ある製品やサービスの開発に必要な要素的技術に対するニーズ、ある特定の技術的課題を解決するための技術的開発に対するニーズなど、技術者集団が持つ技術的ニーズ)の二種類をきちんと区別する必要がある。
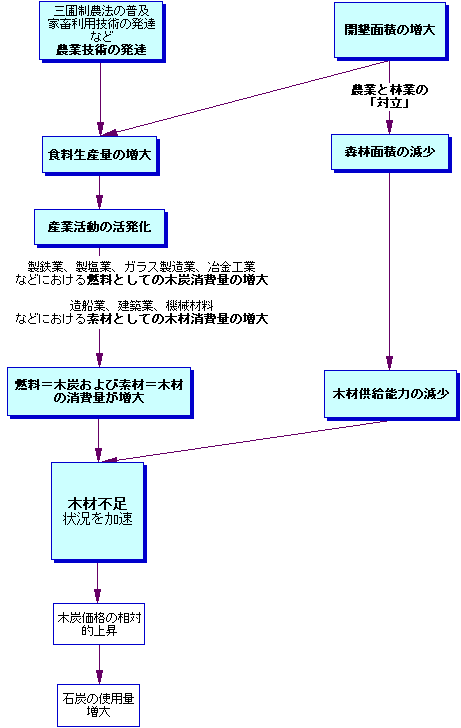
(3)needsとseedsの相互連関的構造 (技術発展のネットワーク構造)
A.ケーススタディ(1)----- 近代ヨーロッパの技術発展
【中世後期ヨーロッパにおける産業革命】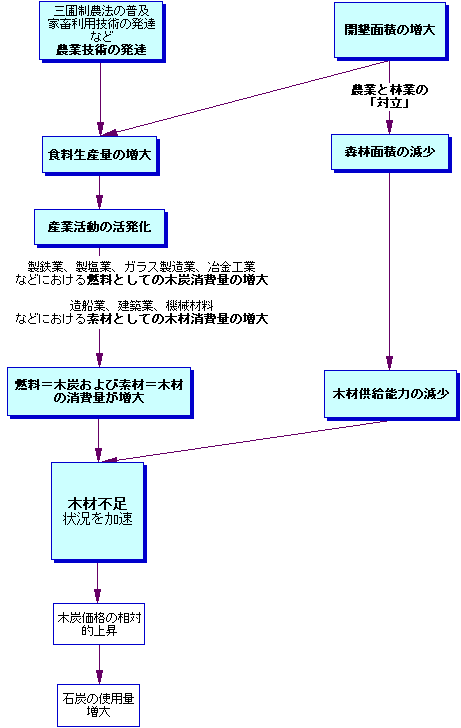
技術革新の進展と普及にともなう一般的な産業発展
歴史的「偶然」 ---- 疾病の流行
14世紀ヨーロッパにおける黒死病(Black Death)>ペストのこと、黒死病による死者は3人に1人といわれ,ヨーロッパでは3500万人,その他を加えると,全文明世界で6000万〜7000万人の死者を数えたと言われている。
↓
「労働力不足」「動力の不足」という社会的ニーズの発生
↓
動力に関するシーズ的技術(既存技術)の利用によるニーズへの対応
既存動力技術の利用にともなって生起した新たな技術革新(技術発展)
---- 動力水車送風機構を用いた高炉製鉄技術による、銑鉄の「大量」生産 -----
銑鉄の「大量」生産という技術革新にともなう新たなニーズの発生(1)
---- 鉄の大量生産にともなう木炭の大量消費という木炭への新たなマーケット・ニーズの発生 ----
銑鉄の「大量」生産という技術革新にともなう新たなニーズの発生(2)
---- 木炭価格の上昇にともなう、大量に生産可能な安価な代替燃料へのマーケット・ニーズの発生 ----
↓-
a-1.<重量犂による深耕などを目的とした家畜動力の利用>や、<二圃制農法から三圃制農法への転換>などの農業技術に関する技術革新
-
三圃制農法(three‐field system)>「耕作地の三分割」と「3年周期の輪作(a.休耕→b.小麦やライ麦などの種を秋に播き夏に収穫[主食用穀物の栽培]→c.大麦や燕麦などを春に播き夏に収穫[家畜用飼料やビール原料の短期的栽培])」を組み合わせることで、土地の利用効率を二圃制の場合の1/2から2/3に上げた技術革新。「家畜動力の利用による深耕」と「家畜の糞の利用による耕作地の肥沃化」といった技術的工夫と組み合わせて実施される。中世初期に登場し、東欧などヨーロッパ北部の平原地帯で中世後期に広く普及した。
[教員用メモ]
歴史的「偶然」 ---- 疾病の流行
14世紀ヨーロッパにおける黒死病(Black Death)>ペストのこと、黒死病による死者は3人に1人といわれ,ヨーロッパでは3500万人,その他を加えると,全文明世界で6000万〜7000万人の死者を数えたと言われている。
↓
「労働力不足」「動力の不足」という社会的ニーズの発生
↓
動力に関するシーズ的技術(既存技術)の利用によるニーズへの対応
- この時代における動力に対する社会的ニーズ(動力需要)は、当時の既存技術(動力水車技術や動力風車技術などといったすでに存在した動力技術)によって満たすことが可能であった。
それゆえ「労働力不足」「動力の不足」という社会的ニーズに対応して、まったく新規の動力技術の開発がなされたというわけではない。
-
動力に関するシーズ的技術(既存技術)
-
動力水車技術
動力風車技術
既存動力技術の利用にともなって生起した新たな技術革新(技術発展)
---- 動力水車送風機構を用いた高炉製鉄技術による、銑鉄の「大量」生産 -----
-
高炉製鉄以前の技術では一日に数kg〜数十kg程度の産出量であったのが、動力水車送風機構を用いた高炉製鉄技術により銑鉄(鋳鉄:ドロドロに溶けた溶融状態の鉄)を生産可能になり、一日にトン単位の生産が技術的に可能になった。
銑鉄の「大量」生産という技術革新にともなう新たなニーズの発生(1)
---- 鉄の大量生産にともなう木炭の大量消費という木炭への新たなマーケット・ニーズの発生 ----
-
中世後期および近代初期における鉄の生産においては、基本的原材料である鉄鉱石よりも大量の木炭を必要とした。その当時は鉄鉱石の約二倍程度もの木炭が必要とされたと言われている。
-
木炭は製鉄プロセスにおいて、「加熱用燃料」であるとともに、酸化鉄である鉄鉱石の「還元剤」(鉄と結合している酸素を引き離すために木炭中の炭素が必要である)、多様な用途を持つ有用物(製品)としての鉄に必要不可欠な「添加物」(炭素という不純物を含まない純粋な鉄は柔らかすぎて、利用範囲は限定されてしまう。炭素が適量混ざることにより、より硬くて適度な展性を持つ有用物としての「鉄」が生産可能になる)といった複合的役割を果たしている。
その結果として、鉄の大量生産は、木炭の大量消費をもたらし、新たな木炭ニーズや代替燃料としての石炭ニーズを生み出すことになった。
銑鉄の「大量」生産という技術革新にともなう新たなニーズの発生(2)
---- 木炭価格の上昇にともなう、大量に生産可能な安価な代替燃料へのマーケット・ニーズの発生 ----
【近代ヨーロッパにおける産業発展】
既存資源である石炭の社会的利用の拡大というイノベーションの発生
代替燃料としての石炭の大量消費=大量採掘にともなう新しいニーズの発生(1)
--- 炭坑深度の増大にともなう湧き水問題の深刻化に対応できる排水技術に対するニーズの増大 ---
「技術の社会的「成功」と社会的「失敗」はneedsとの関係でどのように考えるべきなのか?」という問いに対しては上記のような二つの見解が論理的には可能である。しかしながら「needsとの対応は成功の必要十分条件であるという考え方」はあまりに単純過ぎよう。筆者は、「needsとの対応は成功の必要条件ではあっても十分条件ではない」とすべきだと考えている。
イギリスは、ヨーロッパで最も豊富な露出した石炭層をもっていたこともあり、石炭の利用はローマ時代の紀元4世紀頃にまでさかのぼる、と言われている。(シンガー他編(田中実訳編,1978)『技術の歴史』第5巻,p.60なお中国では2,3千年前から石炭が採掘され、燃料として用いられていたと言われている。前掲書,p.61)
また、13世紀〜16世紀前半までのヨーロッパ地域の中では、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクといった低地諸国で石炭資源が最もよく利用されたと言われている。
ex.イギリスにおける石炭採掘量の歴史的変化
↓また、13世紀〜16世紀前半までのヨーロッパ地域の中では、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクといった低地諸国で石炭資源が最もよく利用されたと言われている。
ex.イギリスにおける石炭採掘量の歴史的変化
1540年頃 約 20万トン/年
1650年頃 約 150万トン/年
1700年頃 約 300万トン/年←明治20年代はじめの日本の生産量にほぼ匹敵
1750年頃 約 450万トン/年
1800年頃 約1000万トン/年
1650年頃 約 150万トン/年
1700年頃 約 300万トン/年←明治20年代はじめの日本の生産量にほぼ匹敵
1750年頃 約 450万トン/年
1800年頃 約1000万トン/年
代替燃料としての石炭の大量消費=大量採掘にともなう新しいニーズの発生(1)
--- 炭坑深度の増大にともなう湧き水問題の深刻化に対応できる排水技術に対するニーズの増大 ---
↓
石炭の大量消費=大量採掘にともなう新しいニーズの発生(2)
--- 大量の石炭を生産地から消費地へと移動する輸送ニーズの増大 ----
-
蒸気動力技術による排水というイノベーションの発生
1700年で約120m,1750年で約180mというような最高深度に達する炭鉱があったことに示されているように、石炭を採掘する深度が深くなるにつれて、既存動力技術(動力水車技術や動力風車技術など)や人間動力・畜力では徐々に対応が困難になってきたために、新しい動力技術である蒸気動力技術に基づく製品の開発が進んだ
↓蒸気動力技術それ自体の引き続く技術的改良(シーズ的技術としての蒸気動力技術の改良)
↓
輸送機関用エンジンおよび工場用動力源・発電所用動力源としての蒸気動力エンジンへ
- 蒸気機関車・工場用定置エンジン・火力発電用エンジンとしての使用を可能にする技術的改良の進展>シーズ的技術を利用した新たな製品の「発明」
石炭の大量消費=大量採掘にともなう新しいニーズの発生(2)
--- 大量の石炭を生産地から消費地へと移動する輸送ニーズの増大 ----
↓
-
「蒸気動力技術というシーズ的技術の活用」と「多管式ボイラーという新しい技術的発明」との組み合わせによる新製品としての蒸気機関車という技術的発明
輸送量が増大するにつれて、既存動力技術(動力水車技術や動力風車技術など)や人間動力・畜力では徐々に対応が困難になってきたために、新しい動力技術である蒸気動力技術に基づく製品[=蒸気機関車]の開発が進んだ
↓鉄道輸送システムという技術革新の進展
蒸気機関車といった技術的発明は、馬による輸送や運河による輸送といったそれ以前の輸送手段に代わる鉄道システムという新しいノベーションを生み出した
↓鉄への新たなニーズの発生
↓
「コークス」ニーズのさらなる増大
-
コークスは、製鉄用燃料、鉄鉱石の還元材、鉄への炭素供給源という三つの役割を持っている。石炭をコークス化することで、製鉄用プロセスで使用することが可能になった。
「石炭」ニーズのさらなる増大
↓
(4)技術の社会的「成功」と社会的「失敗」はneedsとの関係でどのように考えるべきなのか?
見解1>needsとの対応は成功の必要十分条件であるという考え方
needsとの対応の有無が技術の成功・失敗を分ける分水嶺であるという考え方
「needsに対応している技術が成功する」(needsに対応した技術の開発に成功した企業が社会的に成功する)のに対して、「needsに対応していない技術は失敗する」(needsに対応していない技術に固執した企業は社会的に失敗する)という見解。
「社会的「成功」をおさめた技術はneedsに対応していた技術であるし、社会的「成功」に失敗した技術はneedsに対応していなかった技術である」という見解。
「needsに対応している技術が成功する」(needsに対応した技術の開発に成功した企業が社会的に成功する)のに対して、「needsに対応していない技術は失敗する」(needsに対応していない技術に固執した企業は社会的に失敗する)という見解。
「社会的「成功」をおさめた技術はneedsに対応していた技術であるし、社会的「成功」に失敗した技術はneedsに対応していなかった技術である」という見解。
見解2>needsとの対応は成功の必要条件ではあっても十分条件ではないという考え方
needsに対応した技術は一般には複数存在するため、needsに対応していても社会的普及に成功するとは限らない。(needsに対応した技術の開発に成功した企業であっても、社会的に失敗することはある)
「技術の社会的「成功」と社会的「失敗」はneedsとの関係でどのように考えるべきなのか?」という問いに対しては上記のような二つの見解が論理的には可能である。しかしながら「needsとの対応は成功の必要十分条件であるという考え方」はあまりに単純過ぎよう。筆者は、「needsとの対応は成功の必要条件ではあっても十分条件ではない」とすべきだと考えている。
このことは、「needsに対応した技術が一般には一つには限らず複数個存在する」ということを考えれば論理的にすぐに理解できよう。たとえばインターネットという現代的情報通信に対する社会的ニーズに応える技術を例に取ると、次のように複数個存在する。
現在のネット通信に対するニーズの中で、上記の1と3はその技術的性能が他と比べてあまりにも低いために、現在では利用はかなり少なくなっている。
しかし高速ネット通信に対するニーズに応えることのできる技術としても、技術6、技術7、技術8は技術的性能に関して現時点では互いにさほどの差異は存在しない。それらの技術の間での「成功」と「失敗」を分けるものは、高速ネット通信に対するニーズに応えることができるどうかといったneedsへの対応の有無ではなく、別な要因である。
また技術4(xDSL接続技術)は、現時点における最高接続速度は数十Mbpsと他の技術に比べて低いが、それでも普及数は最も高い。総務省報道資料(2005年4月15日)によれば、2004年12月末時点でのブロードバンド回線事業者の加入者数は、CATV回線の契約者数は約290万件、光ファイバー回線の契約者数は約240万件といったように200万件台に留まっているのに対して、DSLの契約者数はそれらの数倍程度の約1330万件に達している。
1.有線電話回線(固定電話回線)の音声帯域を利用した情報通信技術(PPP接続)
2.無線電話回線の音声帯域を利用した情報通信技術(PPP接続)
3.固定音声電話回線(銅線)を利用した情報通信技術(その1)(ISDN接続技術)
4.固定音声電話回線(銅線)を利用した情報通信技術(その2)(ADSL=Asymmetric Digital Subscriber Line(非対称デジタル加入者線))
5.無線を利用した情報通信技術(公衆無線LAN,FWA[Fixed Wireless Access])
6.光ファイバー回線を利用した情報通信技術(FTTH)
7.CATV回線を利用した情報通信技術
8.電線(電力線)を利用した情報通信技術
2.無線電話回線の音声帯域を利用した情報通信技術(PPP接続)
3.固定音声電話回線(銅線)を利用した情報通信技術(その1)(ISDN接続技術)
4.固定音声電話回線(銅線)を利用した情報通信技術(その2)(ADSL=Asymmetric Digital Subscriber Line(非対称デジタル加入者線))
5.無線を利用した情報通信技術(公衆無線LAN,FWA[Fixed Wireless Access])
6.光ファイバー回線を利用した情報通信技術(FTTH)
7.CATV回線を利用した情報通信技術
8.電線(電力線)を利用した情報通信技術
現在のネット通信に対するニーズの中で、上記の1と3はその技術的性能が他と比べてあまりにも低いために、現在では利用はかなり少なくなっている。
2の技術は、回線の通信速度は技術1と同じ程度に過ぎないが、無線の特性=mobility(移動可能性)という優れた技術的特性を持っているがゆえにAirH''の存在に示されているように一定程度のneedsが存在する。
こうした現象は、技術的性能の評価軸の多元性(情報通信技術の技術的性能には、回線速度だけでなく、mobility(移動可能性)や信頼性などもある)という視点から理解すべき問題である。技術的性能の評価軸の多元性の結果として、技術の好適機能範囲が異なることになり、技術の棲み分けという現象が生じることになる。
こうした現象は、技術的性能の評価軸の多元性(情報通信技術の技術的性能には、回線速度だけでなく、mobility(移動可能性)や信頼性などもある)という視点から理解すべき問題である。技術的性能の評価軸の多元性の結果として、技術の好適機能範囲が異なることになり、技術の棲み分けという現象が生じることになる。
しかし高速ネット通信に対するニーズに応えることのできる技術としても、技術6、技術7、技術8は技術的性能に関して現時点では互いにさほどの差異は存在しない。それらの技術の間での「成功」と「失敗」を分けるものは、高速ネット通信に対するニーズに応えることができるどうかといったneedsへの対応の有無ではなく、別な要因である。
また技術4(xDSL接続技術)は、現時点における最高接続速度は数十Mbpsと他の技術に比べて低いが、それでも普及数は最も高い。総務省報道資料(2005年4月15日)によれば、2004年12月末時点でのブロードバンド回線事業者の加入者数は、CATV回線の契約者数は約290万件、光ファイバー回線の契約者数は約240万件といったように200万件台に留まっているのに対して、DSLの契約者数はそれらの数倍程度の約1330万件に達している。
(5)技術の社会的選択に関わる諸要因
2.講義用資料
3.技術経営に関わる参考資料
(1)お薦めWebサイト
(2)関連図書
-
『日経ビズテック』(技術経営戦略をテーマとしている雑誌)
ジョー・ティッド,ジョン・ベサント,キース・パビット(後藤晃・鈴木潤監訳,2004)『イノベーションの経営学』NTT出版
アナベル・ガワー、マイケル・A.クスマノ(小林 敏男監訳,2005)『プラットフォーム・リーダーシップ』有斐閣
マイケル・E.マクグラス(菅 正雄・伊藤 武志訳,2005)『プロダクトストラテジー --- 最強最速の製品戦略』日経BP社
[原書:MacGrath, Michael E.(1994,2nd ed. 2000),Product Strategy for High-Technology Companies]
ヒューゴ・チルキー編(亀岡秋男監訳,2005)『科学経営のための実践的MOT --- 技術主導型企業からイノベーション主導型企業へ』日経BP社
[原書:Tschirky, Hugo,Technology and Innovation Management on the Move]